青山学院大学の教員は、
妥協を許さない研究者であり、
豊かな社会を目指し、
常に最先端の研究を行っています。
未来を創る本学教員の研究成果を紐解きます。
TOPIC
公益財団法人日本漢字能力検定協会とは
「日本漢字能力検定」の実施などを通じて、「日本語・漢字に関する普及啓発・支援」「日本語・漢字に関する調査及び研究」「日本語・漢字に関する能力育成」などの事業を行う団体です。日本語・漢字の学びを支える活動を通じて、「我が国における生涯学習の振興を通じて日本文化の発展に寄与する」(協会理念より引用)ことを目指しています。
共同研究のポイント
生成AIを単なる知識収集の道具にとどめず、生徒が学びを深め、日本語能力を高めていく道具として活用するために、研究成果と教育現場での実サービスを組み合わせることで、新しい教育手法の効果を測ることが可能になります。

トピックを先生と紐解く

益川 弘如 教授
教育人間科学部 教育学科
中京大学 情報科学部 認知科学科卒業。中京大学大学院 情報科学研究科 情報認知科学専攻 博士後期課程 単位取得満期退学、博士(認知科学)。中京大学 情報科学部 認知科学科助手、静岡大学 教育学部講師、同准教授、静岡大学大学院 准教授を経て、2017年4月、聖心女子大学 文学部 教育学科教授。2024年4月より青山学院大学 教育人間科学部 教育学科教授に着任。専門は認知科学、学習科学、教育工学、協調学習。著書に「21世紀型スキル: 学びと評価の新たなかたち」(翻訳)「アクティブラーニングの技法・授業デザイン」(共著)などがある。

人間の学びに関する知見を教育へ応用する学習科学

今後は生成AIなど先端ツールを活用して、さらなる学習の充実を

AIは知識収集のツールだけではなく、対話を通して考えるためのサポート役に
私が研究している「認知科学」とは、人間がどのように物事を認識して自分の知識として取り込むのかを科学的に解明する学問です。さまざまな研究領域の人が集まり、主に「知」、つまり賢さや学びといったものを解明することを目指しています。私自身、大学時代にこの認知科学を専門とする学科に進み、学ぶ中で「人はどのように学ぶのか」「より良く学ぶためにはどのような支援があり得るのか」といったことをずっと研究してきました。
認知科学という学問の領域は学校教育に限らず、日常生活やさまざまな場面における人間の知的活動全般を対象としていますが、1990年代以降にその知見を教育の現場に応用しようという動きが活発化しました。こうした流れの中で生まれたのが「学習科学」です。学習科学では、人工知能(生成AI)を含む多様なテクノロジーの活用も重視されています。従来の学校教育の枠組みにとどまらず、生成AIなどの最先端技術を生かし、より良い学びのかたちを構築することが、現在の学習科学の主要な関心領域です。
もちろん社会状況は時代とともに変わっていきますし、それに応じて教育のあり方を見直す必要があるという考え方も理解できます。けれども、人の学びの原則から考えて、より人の学びの強みを生かした教育のあり方があると考えています。これからの学校教育におけるゴールは、「何を知っているか」で終わるのではなく学んだ事柄を生かして「新たに何ができるようになるか」へと転換していくことが重要だと私は考えています。具体的には、教育者があらかじめ目標を設定する「目標到達型」から、学習者自身が目標を設定する【目標創出型】へと転換すること、そして知識の伝達がメインの「教授中心型」から、学習者が自主体的に学ぶ【学習者中心型】へと移行することが求められます。

学習科学は「人はいかに学ぶか」「どのようなときにうまく学べるか」といった学習理論に基づいています。数十年にわたる研究の積み重ねと新たな情報技術を組み合わせることで、より豊かな学びや教育環境のデザインが可能になります。学習科学を通して【目標創出型・学習者中心型】の学習環境を構築し、その結果としてより良い方向に社会が変わっていけばという思いを抱いています。
教育というのは、誰もが身近に経験してきた分野であるがゆえに、「自分の経験ではこうだった」といった主観的な議論に偏りがちです。けれども、その経験が本当に良い教育だったのか、問題がなかったのかは、どうしても主観に依存してしまいます。そのため、「自分にとってはこの教育が良かった」といった個人の感覚に基づく議論が多くなっていると感じています。しかし本来、教育は科学的に検証されるべき分野です。人の学びに関するデータを集めて分析し、何が有効なのかを明らかにしていくのが学習科学の役割だと思います。
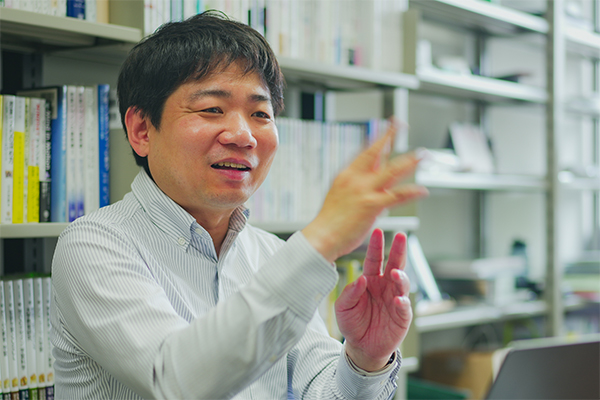
例えば、医学の世界であれば、薬や治療法の効果を測るために、異なる手法のケースを数多く集めて科学的に比較分析することが一般的です。一方で、教育の分野ではそうした定量的な比較が難しく、これまでは優れた教育者の経験則に頼る傾向がありました。これからの教育には、そうした経験を個人の中にとどまる知見として扱うのではなく、データとして記録・分析し、次世代の教育者と共有可能なかたちにしていくことが求められます。私は、こうした科学的なアプローチを通じて【目標創出型・学習者中心型】の教育のあるべき姿を明らかにしていくこと、そしてその成果を現場に還元していくことを研究の目標としています。
日本漢字検定協会は、公式ウェブサイトにも記載されているように「普及啓発・教育支援活動」「調査・研究活動」「日本語能力育成活動」を3つの柱とし、表現力や語彙力など日本語能力全体の向上を目指して活動されています。その活動の一環として、学習科学の知見を応用しながら新しいサービスのかたちを検討できないかということでお声がけをいただいたのが、今回のプロジェクトのきっかけです。
さらに今回は、生成AIの活用も含まれており、日本漢字検定協会が取り扱う「言葉」と、生成AIが扱う「言語情報」は、共通する領域にあります。伝統的な教育手法にとわられず、生成AI技術の進展も柔軟に取り込みながら、学習者の日本語能力を支援する新たな学びのあり方を模索したいというタイミングでもあったのだと思います。学習科学を含む認知科学の分野では、長い期間AI活用の研究をしてきた歴史もあるので、さまざまな要素がこのタイミングでつながった感覚があります。
共同研究をする一番の理由は、企業や団体がいろいろなところに教育サービスを提供しており、それ自体が世の中の教育に貢献していると考えているからです。そうした方々とより良い教育のあり方をともに模索することで、それが巡り巡って社会全体の改善につながることを期待しています。実際には、学習科学的な視点をまだ十分に取り入れてることができていない企業も多く、従来型の教育設計のままサービスが展開されているケースも少なくありません。その場合、対象者の成長に限界が生じてしまうこともあります。だからこそ、私は共同研究を通じて実際にサービスが提供されている現場に働きかけることに、大きな価値を感じています。
学習科学の分野でも、ここ10年ほどで「社会還元」や「社会実装」が重視されるようになり、実践的な展開を意識した“インプリメンテーショナル・リサーチ”の考え方が注目されるようになってきました。私自身にとっても、自分たちの研究や実践から見えてきた「これからの教育や学びの姿」を、いかに社会全体に広げていけるかは、大きな研究テーマのひとつです。
2024年度には、渋谷区の公立中学校で生成AIを活用した授業を実施しました。中学3年生を対象として、自己PR文の書き方を生成AIおよびクラスメイトとともに一緒に考えるという内容です。まず、生徒たちには3年間の学校生活を振り返り、「自分が成長した」と感じたことと、それを裏付けるエピソードを3つ以上挙げてもらいました。次に、生成AIを使ってそのエピソードを比較・分析し、「自分の強みを最も引き出すエピソードはどれか」を考える活動を行いました。AIとの対話は、選択式のボタン形式で行えるように設計し、生徒がエピソード比較のボタンを押すと、AIがそれぞれの特徴を示す仕組みになっています。ただし、生成AIは必ずしも望ましい答えや正しい答えを出すわけではありません。だからこそ、AIの出力結果をもとに、3人組のグループで話し合うプロセスを非常に大切にしました。黙々とAIを使うだけではなく、「こんな結果が出たけど、どう思う?」と友達とともに意見を交わしながら、自己PR文を共同で作り上げていく。その対話の過程こそが重要だと考えています。そうやって議論を重ねて深く掘り下げながら文章化した後は、AIによるチェック機能も活用しました。主張と事実のバランスを確認する機能も用意することで、生徒たちは「この出来事、ちゃんと書けてなかったな」と気付き、試行錯誤を重ねながら文章を何度も練り直していました。

この学習体験の前後で、生徒には「自己PR文を書くうえで大事なポイントは何か」をワークシートに記してもらいました。その内容を分析することで、最初に大事だと思っていたことから、こうした学習活動を経ることで、例えば「事実と意見をしっかり区別して書かなければいけない」と感じた生徒がどのぐらい増えたか、実際の文章にどのような変化が見られたか、生成AIの回答をもとに生徒同士で深い対話が引き出せたかなどをチェックして、システムの評価を行っています。
ただ、このような文章作成のスキルは短期間で習得できるものではありません。そのため将来的には、中学校の国語の授業のような継続的な学習の中で、生成AIを適切に活用しながら、生徒たちがこの技術をしっかりと自分の力として定着していけるのか。それともアプリを使った直後の一時的な効果にとどまってしまうのか。そうした点も含めて今後も丁寧に検証していく必要があると考えています。
相模原市の公立中学校では、先生が事前に授業用に考え用意したプロンプトを使用し、生徒が生成AIからの質問に答えたり、その答えをもとに生徒同士で対話しながら学習理解を深めていく授業を実施しています。例えば、クラスメイトと生成AIの力を借りて、人間とAI双方の特性を生かしながら持久走の質を高めるといった試み行われており、主要教科にとどまらず、美術や保健体育などさまざまな場面で学習にAIをどのように生かしていけるかというチャレンジを行っています。
こうした取り組みで欠かせないのは、AIの回答をそのまま受け入れて終わるのではなく、それをいかにクラスメイト同士の議論を行うかなど、自分たちで考えるきっかけを作っていくことだと考えています。あまり工夫をしないまま学習に生成AIを導入すると、生徒は「AIに聞けば答えが出る」といった受け身に陥ってしまいがちです。しかし、AIはあくまでも”プラスα”の存在であり、学びの中心にあるべきなのは、人との対話や自分で考える力です。そうした学習のあり方を、今後も大切に育んでいきたいと考えています。
これまでは、生成AIや情報端末を通じて、中学生をはじめとする学習者が「読み書きする力」、すなわちリテラシーを身に付けることに重点が置かれてきました。しかしこれからは、そうした基礎的な力を土台としつつ、先端技術の活用と人間同士の対話を組み合わせ、より高度なリテラシーを育む教育へと移行していく必要があります。実際に、そのような変化は少しずつ始まりつつあります。
今後は、子どもたちが生成AIツールを活用しつつも、子どもたち同士で対話しながら学びを深めていけるような学習支援システムや授業づくりをサポートしていきたいと考えています。学部や大学院のゼミにおいても、学生も一緒になってそのような学習支援のあり方を一緒に検討しています。さらに、それらアイデアを中学校や高等学校の現場で活用・検証し、日本漢字能力検定協会と進めているプロジェクトの完成度を高めながら、より実践的な形で展開していくことを目指しています。
